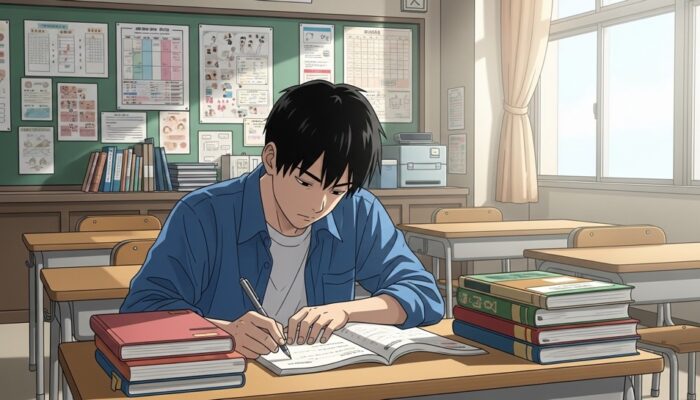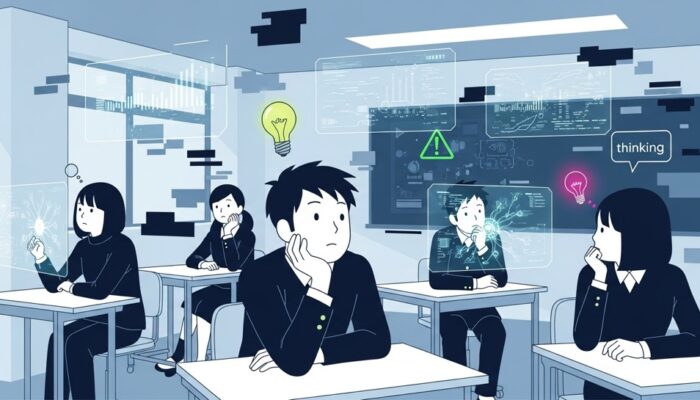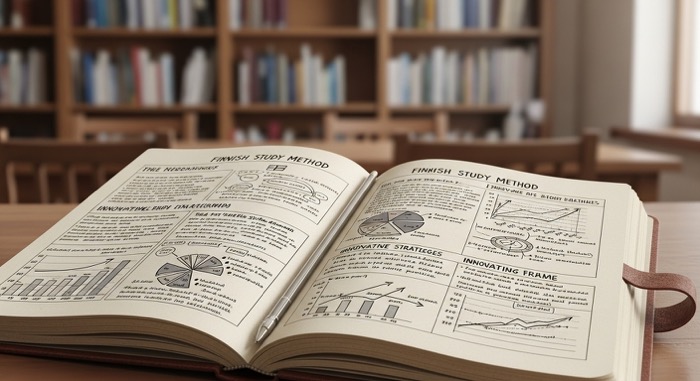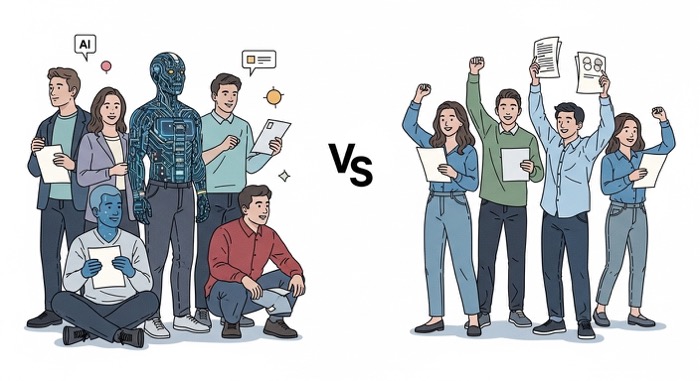間隔反復学習が記憶に与える科学的根拠
スペースド・リピティションの科学的な根拠となっているのが、以前にもご紹介した「エビングハウスの忘却曲線」です。人は何かを学んでも、1日後にはその7割以上を忘れてしまいます。
しかし、忘れかける絶妙なタイミングで復習すると、記憶はより強く、長期間保持されるようになります。スペースド・リピティションは、この「忘れかけた頃に思い出す」というプロセスをシステム化したもの。
つまり、復習の「間隔」を徐々に広げていくことで、脳に「この情報は重要だ!」と何度も認識させ、長期記憶へと定着させるのです。
ドイツの心理学者が発見した最適復習タイミング
では、その「最適な復習タイミング」とはいつなのでしょうか?この研究の元祖であるドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスの研究などを基に、一般的に効果的とされるタイミングがあります。
効果的な復習スケジュール
- 1回目の復習:学習した次の日
- 2回目の復習:1週間後
- 3回目の復習:2週間後
- 4回目の復習:1ヶ月後
もちろんこれは一例ですが、ポイントは「復習の間隔をだんだん長くしていく」ことです。この法則に従うことで、無駄な復習を減らし、最小限の努力で最大限の記憶効果を得ることができます。
Ankiアプリを使った単語学習の自動化
この最適な復習タイミングを、自分で管理するのは大変ですよね。そこでおすすめなのが、「Anki」のようなスペースド・リピティションのアルゴリズムが組み込まれたフラッシュカードアプリです。
Ankiに覚えたい単語や事柄を登録すると、アプリが自動で最適な復習タイミングを計算し、毎日「今日復習すべきカード」を出題してくれます。
ユーザーは、そのカードを見て「思い出せたか」「思い出せなかったか」を答えるだけ。このシンプルな作業を繰り返すだけで、科学的に正しい復習が自動でできてしまうのです。語学学習や専門用語の暗記に絶大な効果を発揮します。
資格試験に活かす復習スケジュール作成法
範囲の広い資格試験の勉強にも、この考え方は応用できます。
システム構築の手順
- 学習単元を細かく分ける:まず、テキスト全体を「第1章-1」「第1章-2」のように、15~30分で学べる小さなユニットに分割します
- 学習日と復習日を記録する:スケジュール帳やエクセルで、各ユニットを「いつ学習したか」を記録します
- 復習日をセットする:学習したユニットに対して、「翌日」「1週間後」「1ヶ月後」の欄にチェックマークや日付を入れ、その日に必ず復習するようにします
この仕組みを作ることで、試験範囲全体を計画的に、かつ効率的に記憶に定着させていくことが可能になります。やみくもな勉強から卒業し、科学的な復習システムを手に入れましょう。
Ankiはパソコン(Windows、Mac、Linux)だけでなく、スマートフォン(iOS、Android)にも対応しており、無料のAnkiWeb同期サービスを使えば、どの端末からでも自分のカードを管理・学習できます。カードにはテキストだけでなく、音声・画像・動画・数式なども自由に追加できるため、英語のリスニングや理系科目の学習にも最適です。
さらに、カードのデザインや表示タイミングを自分好みに細かくカスタマイズできるのも魅力です。10万枚を超える大量のカードもスムーズに扱える高いパフォーマンスを持っています。また、世界中のユーザーが作成した「共有デッキ」をダウンロードして、すぐに学習を始めることもできます。
オープンソースで開発されており、有志による機能追加や翻訳、デッキの共有など、コミュニティの力で進化し続けています。アドオン機能を使えば、標準機能に加えて多彩な拡張も可能です。Ankiは「記憶を偶然に任せず、自分の意思でコントロールできる」学習ツールとして、多くの日本人学習者におすすめできるサービスです。