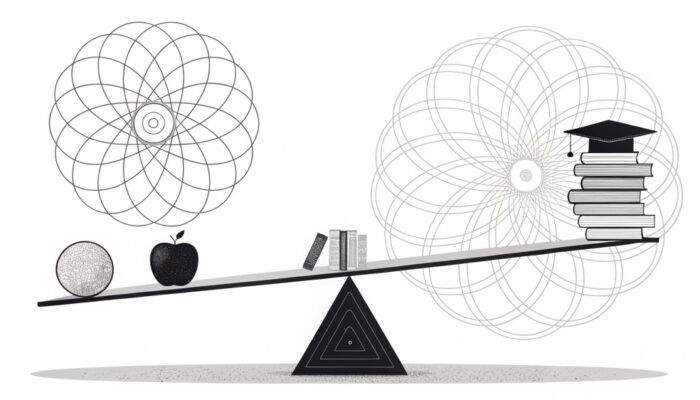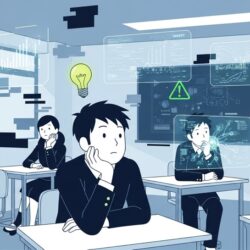普遍的価値としての「人権」と学校現場の現実
人権は、現代社会において疑いようのない普遍的な価値であり、誰もがその尊厳を尊重されるべきであることは自明の理です。しかし、日本の学校現場、特に戦後の教育を長きにわたり牽引してきた日本教職員組合(日教組)による人権運動は、その理想を追求するあまり、時に「行き過ぎた」と評される様相を呈し、それが教育現場に複雑かつ深刻な影響を与えてきたことは、真摯に検証すべき重要な課題です。
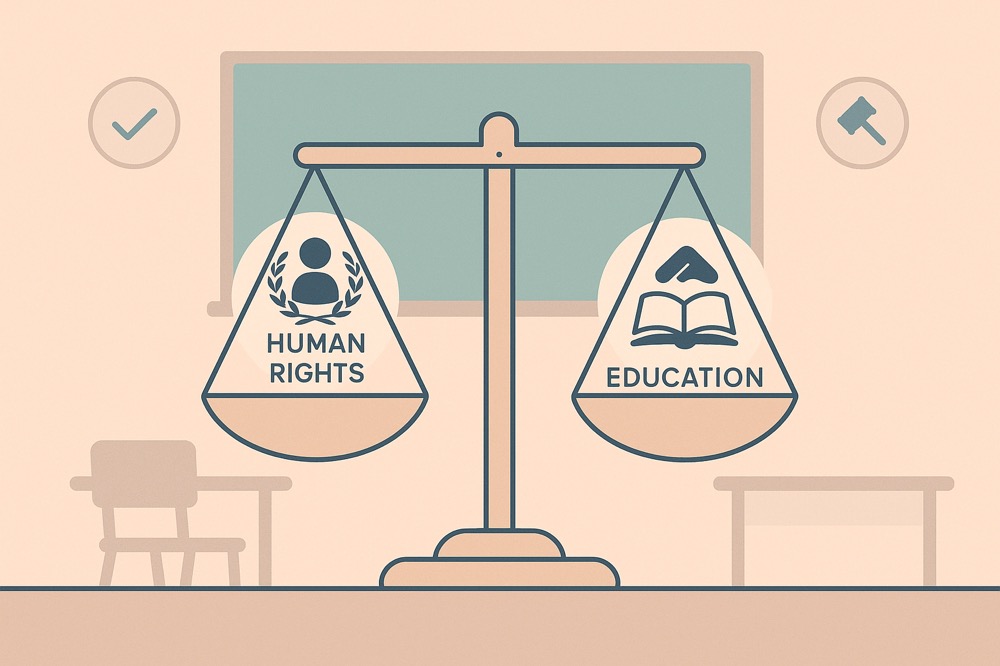
「支援」の名の下に失われた「指導」の意義
「支援」という教育アプローチが学校現場に導入された際、「指導はダメだ、支援なのだ」といった極端な言説が一部で蔓延したことは、その典型的な事例と言えるでしょう。個々の児童生徒の多様性を尊重し、それぞれのニーズに応じたきめ細やかな支援を行うことの重要性は、現代教育において不可欠な要素です。
発達障害を持つ児童生徒への個別指導、経済的困難を抱える家庭への配慮、あるいは多様な文化的背景を持つ子どもたちへの理解など、個に寄り添う「支援」の価値は計り知れません。しかし、それが「指導」そのものを排斥し、あるいは過度に忌避するような解釈に至ったとき、教育本来の目的は大きく歪められる危険性を孕みます。
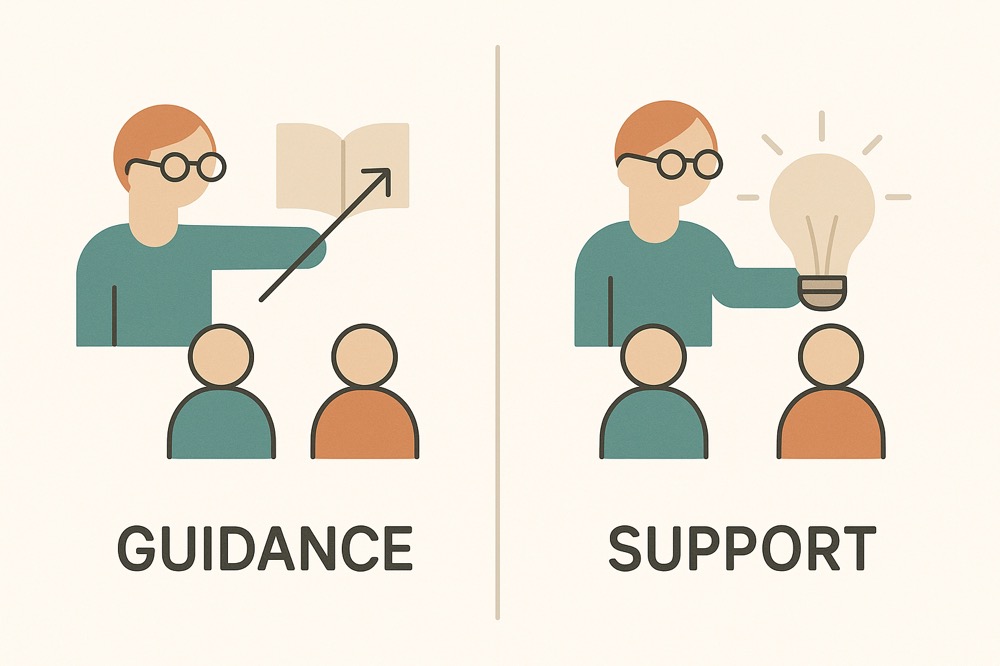
教育は、単に個人の権利を保障するだけでなく、社会の中で自立し、他者と共生していくために必要な規範意識、規律、社会性を育む場でもあります。例えば、集団行動におけるルール順守、他者への配慮、あるいは困難に直面した際の粘り強さといった、時に厳しさを伴う「指導」によって培われるべき資質があります。廊下を走らない、授業中は私語を慎む、友達の物を勝手に使わないといった基本的なルールを教えること。あるいは、いじめや差別を許さない毅然とした態度を示すこと。これらは、児童生徒が社会の一員として健全に成長していく上で不可欠な「指導」です。
しかし、「指導」が「人権侵害」と短絡的に結びつけられ、教員が指導に及び腰になる風潮が生まれた結果、児童生徒が社会性を身につける機会が失われ、自己中心的傾向が助長されるといった弊害が指摘されるようになりました。
授業中にスマートフォンを操作する生徒を注意できない、宿題を提出しない生徒に強く指導できない、あるいはクラス内で孤立している生徒に積極的に働きかけられないといった状況は、教員の専門性や熱意を削ぎ、教育の質の低下を招きます。また、「支援」が過度に強調されるあまり、責任の所在が曖昧になるケースも見受けられました。
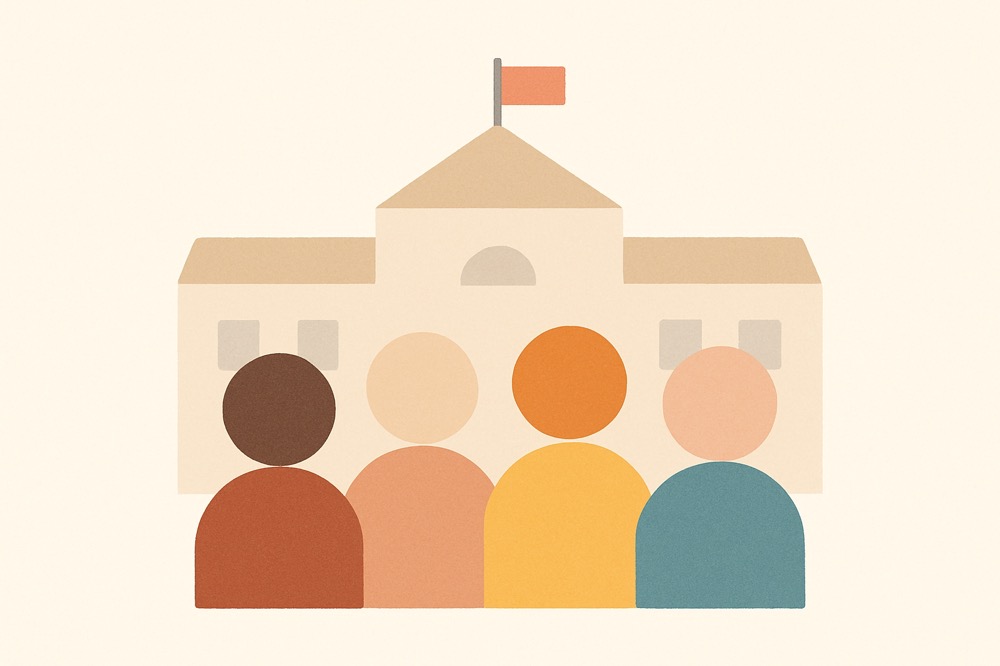
本来、児童生徒の成長には、教員が明確な方針をもって指導し、時に厳しく叱責することも必要です。例えば、万引きやいじめといった問題行動に対し、毅然とした態度で指導し、再発防止に向けた具体的な措置を講じることは教員の重要な責務です。しかし、「支援」の名の下に、問題行動が個人の特性や環境に起因するものとされ、介入や指導が避けられることで、結果として問題が深刻化する、あるいは周囲の児童生徒にしわ寄せがいくといった状況も生じました。
これは、「個」の尊重が「集団」の秩序や安定を脅かすという、教育現場における逆説的な事態を招いたと言えるでしょう。集団の中で生きる上でのルールやマナーが曖昧になり、一部の児童生徒の行動が他の児童生徒の学習権や安全を脅かす事態に発展することもありました。
多様性の名の下に生じる「分断」と「過剰なコンプライアンス」
人権意識の高まりは、社会における個人の多様性を認め、尊重する価値観を浸透させる上で不可欠な原動力となりました。性自認の多様性、民族的背景の多様性、宗教的信条の多様性など、あらゆる個人が尊重されるべきであるという理念は、現代社会の基盤です。しかし、それが「主張すれば良い」という風潮に傾倒すると、建設的な対話が困難になり、かえって学校内の「分断」を招くことにつながります。
例えば、特定の主張や少数派の意見が絶対視され、それに異を唱えること自体が「人権侵害」と見なされるような状況が生じれば、健全な批判的思考や意見交換の場が失われます。学校は、様々な意見を持つ人々が集まる小さな社会です。そこで、ある特定の意見だけが「正解」とされ、それに反する意見が「不適切」として封じられるようなことがあれば、それは民主主義社会の基盤となる対話と合意形成のプロセスを阻害し、最終的には学校という共同体の一体感を損なうことになりかねません。
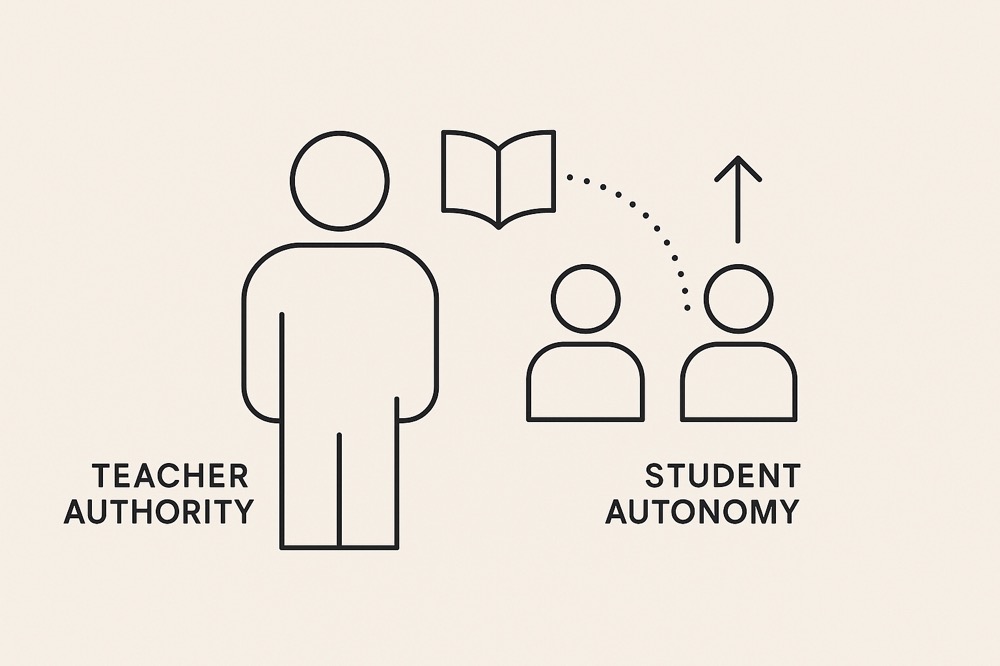
自分の意見だけが正しく、他者の意見を受け入れられないという姿勢は、多様性の尊重とは程遠い、新たな形での不寛容を生み出す危険性をはらんでいます。さらに、行き過ぎた人権意識は、学校現場に過剰なコンプライアンス意識を根付かせる結果となりました。
あらゆるリスクを回避しようとするあまり、教員は萎縮し、自律的な判断や創造的な教育活動が著しく制限されることになります。例えば、運動会や遠足といった学校行事の実施においても、万が一の事故やクレームを恐れて過度に安全基準を設けたり、生徒指導においても、不適切な言動が「パワハラ」や「いじめ」と指摘されることを恐れて毅然とした態度が取れなくなったりするといった事例が散見されます。
かつては当たり前だった組体操が中止されたり、宿泊行事での自由時間が大幅に制限されたりするなど、子どもたちの成長にとって貴重な経験の機会が失われることもあります。
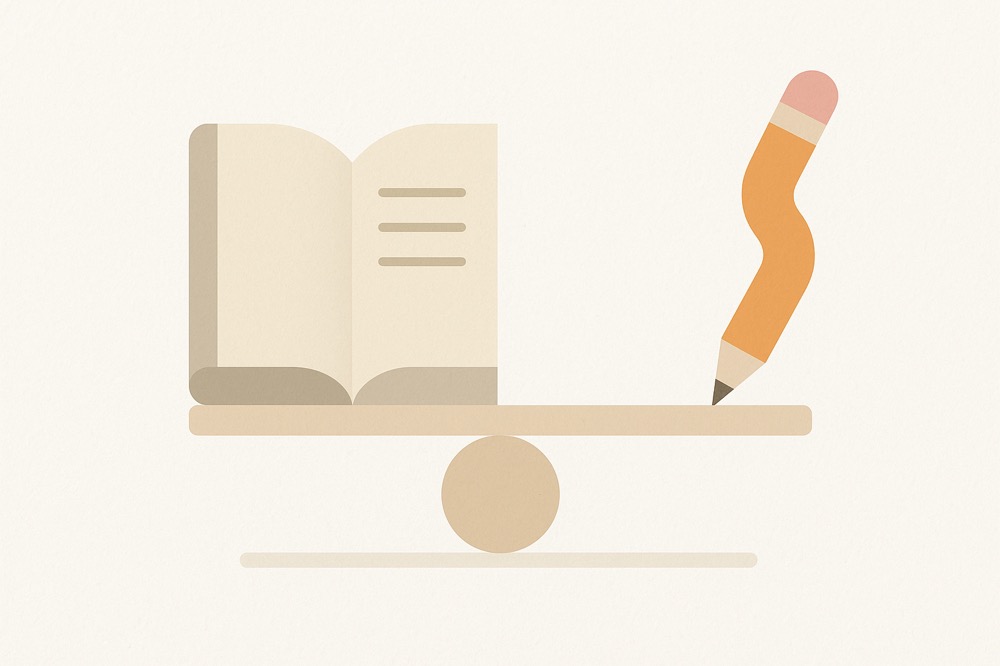
これは、教員の「専門性」や「裁量」を奪い、学校教育を硬直化させる要因となります。子どもたちの主体性や創造性を育むためには、教員が自らの判断で柔軟に対応し、時にはリスクを冒してでも挑戦的な教育活動を行うことが不可欠です。しかし、過剰なコンプライアンスは、そうした教育の営みを阻害し、結果として子どもたちの成長の機会を奪うことにつながります。
教員が常にリスクを回避することに神経を使い、本来の教育活動に集中できない状況は、教員のストレスを増大させ、ひいては教員不足や離職といった問題にも繋がっています。