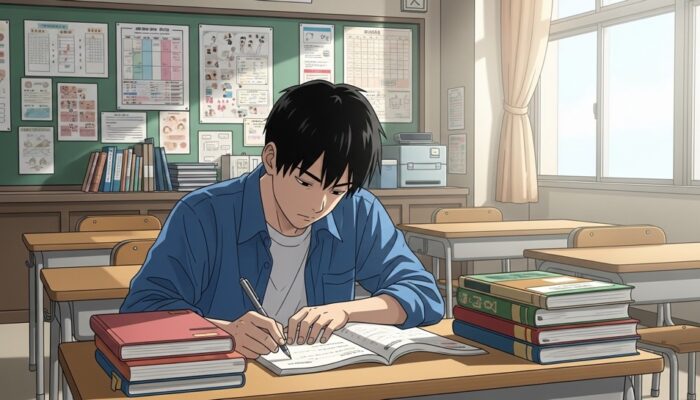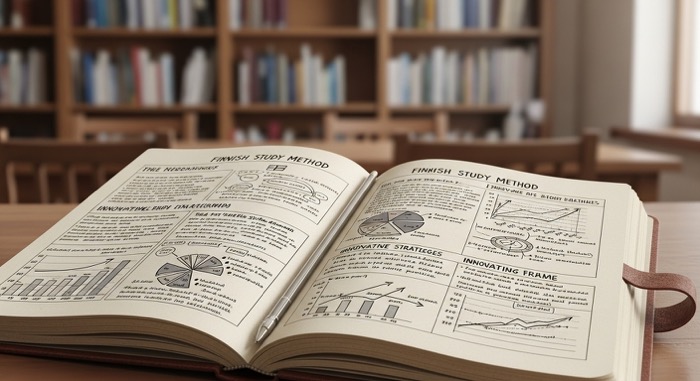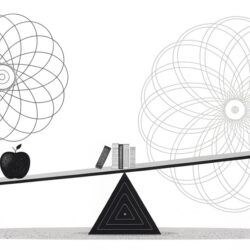「いい大学=成功」は本当か?──学歴神話の正体
「少しでも偏差値の高い学校へ…」という親心は、今も昔も変わらず多くの家庭で語られています。子どもの将来を思うからこそ、より良い環境を与えたいという願いは自然なものです。進学や学歴が人生の成功につながると信じて疑わない人も少なくありません。しかし、果たしてそれは本当に子どもの幸せに直結するのでしょうか。
「いい大学に行った方が当たりの多いクジを引けるのは間違いないと思う」という意見も目につきます。確かに、有名大学に進学すれば、選択肢が広がり、出会いやチャンスも増えるように見えます。企業の採用や社会的な評価において、学歴が有利に働く場面があることも否定できません。

しかし、この「当たりの多いクジ」という発想には、人生を単なる運や確率のゲームとして捉えてしまう危険性があります。実際には、どんな大学に進学しても、その人自身の努力や行動、価値観によって人生の道は大きく変わります。
最新の研究でも、「学校に入ったから能力が伸びる」のではなく、もともと能力が高い子が難関校に入りやすいという事実が明らかになっています。つまり、同じ能力を持つ子どもがどの大学に進学しても、その後の人生に大きな差は生まれないというのです。
「当たりクジ」思考が子どもを苦しめる理由
「いい大学に行けなかったから不利だ」「当たりが少ないクジしか引けない」という考え方は、子どもや若者に無力感や拗ねる気持ちを植え付けてしまいかねません。
努力しても報われない、環境がすべてだという諦めの感覚が広がると、挑戦する意欲や、自分らしく生きる力が失われてしまいます。こうした風潮は、子どもたちの心に深い影響を与え、将来への希望や自信を奪ってしまうことさえあります。
むしろ、無理をしてギリギリの学校に入った場合、学業についていけず自信や意欲を失ってしまうリスクもあることが研究で示されています。学歴や偏差値だけにとらわれて「背伸び」をさせることは、必ずしも子どもの幸せにつながるとは限らないのです。

子どもに合った環境こそが「本当の当たり」
では、親として本当に大切なことは何でしょうか。それは、「その子に合った環境を選ぶこと」です。一人ひとりの個性や適性を大切にし、その子に最適な場所で伸び伸びと成長できる環境を選んであげることこそが、親の愛情のかたちなのではないでしょうか。
教育現場でも、子どもが自分で考え、判断し、行動する力(=自律)を育てることが重視されています。失敗を恐れず、挑戦する気持ちを育むためには、親が過度に先回りせず、子どもに選択の自由を与えることが重要です。例えば、学校でのクラブ活動や週末の過ごし方など、小さな選択から始めてみる。親は子どもの選択を尊重し、失敗してもその経験から学ばせる姿勢を持つことが大切です。

また、親が子どもの話に耳を傾け、安心感を与えることで、子どもは自己表現が豊かになり、自分の意見や感情を自由に表現できるようになります。
勉強や進路についても、親が「どんなことが知りたい?」と興味を引き出し、子ども自身が興味を持って取り組むように促すことが大切です。無理に勉強を強要するのではなく、子どもが自分で学びたいと思える環境を整えてあげることが、長い目で見たときの成長につながります。
最後に、親としてできる最大のサポートは、子どもを一人の人間として尊重し、その可能性を心から信じることです。どんな道を選んでも、そこで何を学び、どう成長するかが人生の「当たり」を決めるのです。学歴神話にとらわれず、子どもたちが自分の力で未来を切り拓いていけるよう、温かく支えていきましょう。
日本国内の代表的な研究として、神戸大学と同志社大学による2万人規模のアンケート調査があります。この調査では、所得や学歴よりも「自己決定(自分で進路や職業を選ぶこと)」が幸福度に強く影響することが示されました。学歴は統計的に有意な要因ではなく、健康や人間関係、自己決定の方が幸福感に直結するという結果です。詳細は神戸大学ニュースサイトや、独立行政法人経済産業研究所(RIETI)のディスカッション・ペーパーで公開されています。
所得や学歴より「自己決定」が幸福度を上げる
人間の幸福と健康