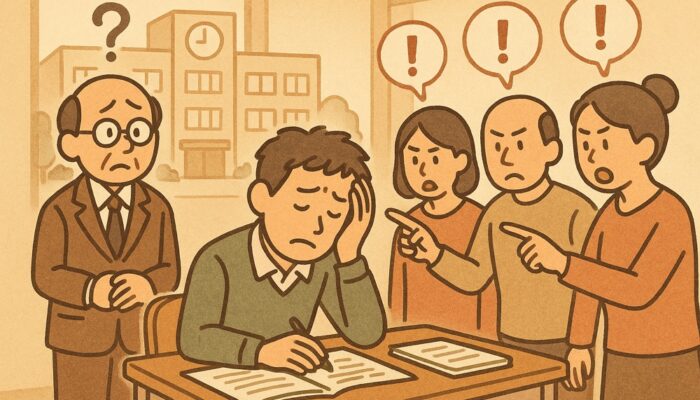子育てと学習における予測誤差の役割
「子育ては、予測誤差をうまく扱うための営み」と言い換えることもできます。
私たちは、子どもがより正確に世界を予測できるように、日々の経験を通してサポートしているのです。
優れた先生は予測誤差を操る
たとえば、小学校の先生は、この予測誤差をうまく利用しています。
算数の授業で、先生が意図的に「あれ?教科書と答えが少し違う計算問題」を出すことがあります。
子どもたちは「え?どうして?」と疑問を持ちますよね。
この小さな予測誤差が、学習意欲を引き出すきっかけになります。
先生は、その疑問を一緒に解決することで、子どもたちは自分で答えを見つけ出し、より深い知識を身につけます。
こうして、予測誤差を小さくする力、つまり「考える力」が育っていくのです。
予測誤差は成長のチャンス
予測誤差は、ただの失敗ではありません。
むしろ、子どもが成長するための大事なエンジンです。
脳は、予測が外れた理由を考え、新しい情報を探します。このプロセスこそが「学習」そのものです。
例えば、種子の発芽の条件を学ぶ学習が小学校の理科にあります。
発芽するために必要なものは何でしょう?
との教師の問いに、子どもたちはいろいろに考えます。
水!
空気!
日光!
など子どもたちはこれまでの生活経験の中で予想します。
この予想を予測と言葉を置き換えてもいいでしょう。
実際に実験観察すると、種子の発芽の条件は、水、空気、適切な温度ですが、日光!と予測していた子どもたちはけっこう多く、日光が植物の発芽に必要ないことに驚きます。
これも予測誤差です。
しかし、この予測誤差が新たな学びのきっかけにも同時になっています。
子どもによっては、予測誤差から学習意欲が増す子もいます。
このように、予測と現実のズレを認識し、どうすればそのズレをなくせるかを考えることができます。
この繰り返しの営みが、子どもの脳と心を形作り、たくましく成長させるために不可欠なものなのです。