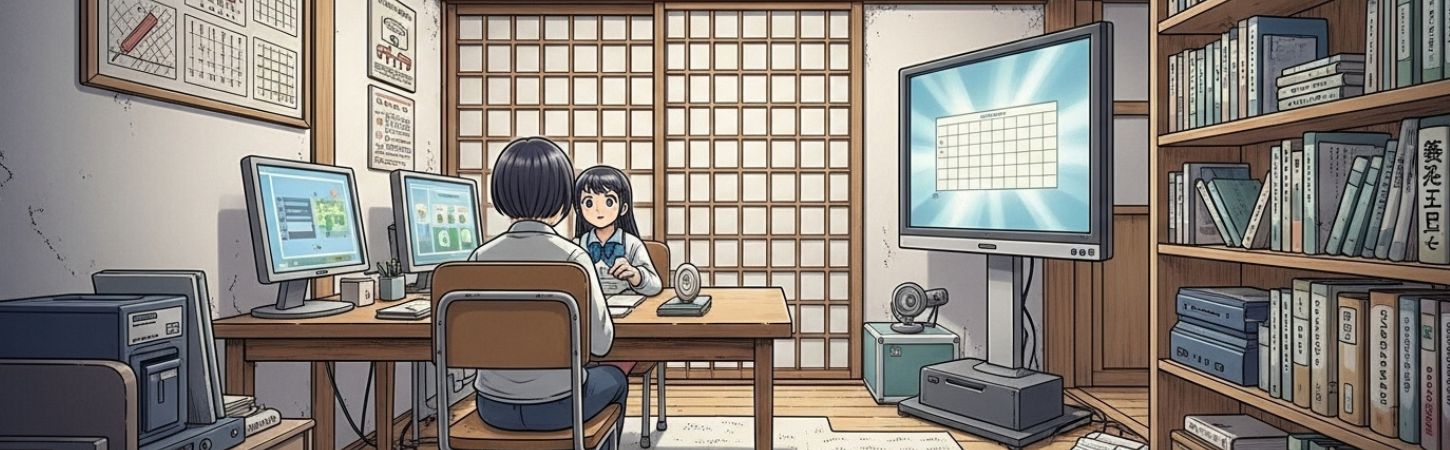国内教育ニュース
文部科学省の概算要求が公表され、教員不足対策や高校無償化に関する動きが活発になっています。特に、中学校での少人数学級や教科担任制の拡大に向けた教員定数増は、現場の負担軽減と教育の質の向上に直結する重要な方針です。一方で、政治判断が待たれる高校無償化の具体的な金額が示されなかったことや、私立高校への支援拡充に伴う公立高校の今後への懸念も浮上しており、今後の動向が注目されます。また、夏休み明けの不登校問題や、古典教育の現代的意義についても、社会の関心が高まっています。
28年度までに約3万人の定数改善を計画 文科省の概算要求
文部科学省は来年度予算案として、前年度比10.0%増となる6兆599億円の概算要求を公表しました。特に教員不足の解消に向け、中学校での35人学級実現や小学4年生への教科担任制拡大を目的として、9,214人の定数改善を求めています。さらに、2028年度までに合計2万9,621人の教職員を増やす新たな「定数改善計画」を策定し、教員不足に対応するため「日本版サプライティーチャー制度」の検討も始めています。
更新日:2025-08-29
引用元:教育新聞
無償化対応で文科省に「高校振興課」新設へ 来年度、公立高支援など
文部科学省は、来年度から予定されている私立高校の授業料無償化を見据え、概算要求に「高等学校振興課(仮称)」の新設を盛り込みました。これは、2026年度からの私立高校の就学支援金について、所得制限をなくして年間45万7,000円を上限に支給することで、与党3党が合意したことに対応するものです。私立高校への手厚い支援により、公立高校離れや専門高校の定員割れが進むことを懸念し、公立高校への支援拡充を含めた教育の質の確保が課題となっています。
更新日:2025-08-29
引用元:教育新聞
古典教育はなぜ必要か 情報の真偽、見定める力に
高校の国語科で学ぶ古文・漢文は、若者を中心にその必要性が問われることが少なくありません。しかし、武蔵野大学の特任教授は、フェイクニュースが飛び交う現代において、情報の真偽を見極める力を養う上で古典教育は不可欠だと主張しています。古典文学を深く読み解くプロセスを通じて、歴史的背景や著者の意図を考察する力、そして多角的に物事を捉える力を培うことが、現代社会を生き抜く上で重要なスキルとなるという視点から、古典教育の新たな価値を提示しています。
更新日:2025-09-01
引用元:日本経済新聞
夏休み明け、子どもの不登校にどう対応? 小中学生の支援員に聞く
夏休み明けは、子どもの不登校が増加する傾向にあります。その背景には、生活リズムの乱れや人間関係、学習への不安などが複雑に絡み合っていると、広島県の教育支援センター長は分析しています。大切なのは、まず子どもにとって安心できる居場所を作ること。学校復帰だけを目標とするのではなく、相談する力や自己をコントロールする力を育むことで、長期的な視点での自立を支援する方針が重要であると指摘しています。
更新日:2025-08-31
引用元:朝日新聞
「高校無償化」は金額示さず、来年度予算の概算要求 政治の結論出ず
文部科学省は来年度予算の概算要求を公表しましたが、高校授業料の無償化拡大については金額を明記しない「事項要求」となりました。自民・公明・日本維新の会の3党が、私立生向けの就学支援金を所得制限なしで年45万7千円まで拡大することで合意したにもかかわらず、留学生や外国人学校、通信制高校の扱いについて結論が出ず、政治主導の制度設計が間に合わなかったためです。これにより、今後の議論の行方に注目が集まっています。
更新日:2025-08-29
引用元:朝日新聞
今週の国内教育ニュースまとめと考察
今週の国内教育ニュースは、国の教育政策の骨格を形成する概算要求を中心に、教員不足や不登校、高校無償化といった喫緊の課題への対応が報じられました。特に、教員定数改善に向けた具体的な計画が示されたことは、多忙化が問題視される教員労働環境の改善と、少人数学級によるきめ細やかな指導の実現に向けた第一歩と評価できます。また、古典教育や不登校問題への専門家の見解は、教育が単なる知識の伝達に留まらず、現代社会を生き抜くための本質的な力を育む場であるべきことを再認識させてくれます。政治的な決着がついていない高校無償化の議論も含め、私たちは今後の政策決定プロセスに注目し、社会全体で教育の未来を考えていく必要があります。
海外教育ニュース
今週の海外教育ニュースは、アジアの教育大国シンガポールや、教育移住先として注目されるマレーシアの現状、そしてアメリカ、韓国、フィンランドの教育課題に焦点が当たりました。シンガポールのPISAにおける驚異的な成果や、韓国の携帯電話使用禁止法案は、教育における成果と管理のバランスについて問いを投げかけています。一方で、マレーシアでの転校の多さや、フィンランドの学力低迷は、教育のあり方が国や文化によって多様であることを示しています。
読解力も、数学も、科学もすべて”世界1位”…この10年で教育大国になった「中国ではない」アジアの国とは
OECDの学習到達度調査「PISA」で全科目1位となったシンガポールに注目が集まっています。天然資源を持たない同国は、初代首相リー・クアンユー氏が「唯一の資源である人材の育成」を国家戦略の中心に据え、教育を重視してきました。1980年代から導入された能力別のコース分けや、「考える学校、学び続ける国家」という理念の下で構築された厳格な競争システムが、今日の高い学力に結びついていると分析されています。
更新日:2025-08-29
引用元:プレジデントオンライン
「同級生の半分も転校してしまうの…?」マレーシアに教育移住した日本人が見た”驚きの実態”
教育移住先として人気が高まっているマレーシアですが、インターナショナルスクールでは転校が頻繁に発生している現状が明らかになりました。クラスの半数近くが入れ替わることもあると、移住した日本人家族は語っています。この背景には、保護者が子どもの学習ニーズや成長に合わせて積極的に学校を変える文化があります。多民族国家ならではの多様な文化に触れられる一方で、教育環境の流動性の高さが特徴的です。
更新日:2025-08-31
引用元:東洋経済オンライン
アメリカ国土安全保障省、国際学生の滞在期間制限を提案
アメリカの国土安全保障省が、国際学生の滞在期間を最長4年に制限する新たな規則を提案しました。これまでは、学生ビザを持つ限り在学中は滞在が可能でしたが、新規則は博士課程の完了や学士号取得に必要な平均期間よりも短い制限となります。トランプ政権下で国際学生への規制が強化されており、すでに6,000件もの学生ビザが取り消された事例もあります。教育関係者は強く反対しており、今後の動向が注目されます。
更新日:2025-08-29
引用元:Inside Higher Ed
韓国、授業中の携帯電話使用を禁止!保護者・教師・生徒が衝突
韓国国会が、2026年3月から授業中の携帯電話やスマートデバイスの使用を禁止する新法を可決しました。韓国の中高生の約37%がSNSの影響を受け、10代の43%が携帯電話に過度に依存しているという背景があります。支持派は学習への集中力向上を期待する一方、反対派は学生の権利制限や根本的な解決策にならないと批判。オランダでの先行事例では集中力向上の効果が報告されており、その是非が議論されています。
更新日:2025-08-28
引用元:VOCOニュース
「フィンランド」はもう”学力世界一”ではない…日本の学校のお手本だった”教育大国”の意外な現在
かつて「教育大国」として日本の教育界でも注目を集めたフィンランドですが、近年、学力が低迷している現状が報じられました。フィンランド国家教育庁は、家庭の社会経済的不平等、教育資源の格差、ソーシャルメディアの影響、メンタルヘルスの問題などを学力低下の要因として挙げています。興味深いのは、フィンランドの子どもたちは数学に対する不安が少ないにもかかわらず、必ずしもそれが好成績に結びついていない点であり、学力と学習意欲の関係について新たな問いを投げかけています。
更新日:2025-08-28
引用元:プレジデントオンライン
今週の海外教育ニュースまとめと考察
今週の海外教育ニュースは、シンガポールやフィンランドといった教育先進国の光と影を映し出しています。シンガポールの厳格な競争システムがPISAでの圧倒的な成果に繋がっている一方、フィンランドの学力低迷は、教育が直面する社会経済的な不平等やデジタル化の影響といった現代的な課題を浮き彫りにしています。また、韓国の携帯電話禁止法案は、テクノロジーが学習に与える影響と、それにどう向き合うべきかという普遍的な問いを投げかけています。これらのニュースは、各国の教育システムが、その社会や文化、そして時代の変化にどう適応しようとしているかを示唆しており、私たち自身の教育観を再考する良い機会を与えてくれます。