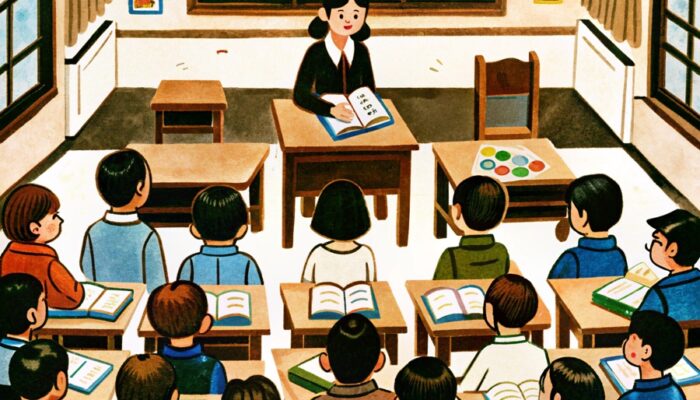日教組の責任
これら日教組の活動、そして学校の崩壊という状況は、日教組が教育現場において負うべき重大な責任を明確にしています。
1. 教育の政治的中立性の侵害
当時の教育基本法(旧法)第8条は、「教育は、不当な支配に服することなく、教育本来の目的を達成するように行われなければならない」と定め、教育の政治的中立性を厳しく求めていました。しかし、日教組の活動は、この原則に反し、特定の政治的立場や思想を学校教育に持ち込み、児童生徒にそれを植え付けようとしたと批判されてきました。
教師は、児童生徒に多様な価値観を提示し、自ら考える力を育む役割を担っています。しかし、日教組の活動は、その役割を放棄し、教師の立場を利用して自身のイデオロギーを広める手段として教育を利用したと指摘されても仕方がありません。
これは、教師の職務に対する信頼を根本から揺るがす行為です。
2. 児童の健全な思想形成および学習機会の阻害
幼い頃の教育は、その後の人生における思想や価値観の基盤を形成する上で極めて重要です。日教組の活動は、児童に対し、特定の歴史観や社会観、国家観を一方的に提示することで、多角的でバランスの取れた思考力を育む機会を奪った可能性があります。
さらに、授業が成り立たない学校環境は、児童の基礎学力向上を妨げ、学習機会そのものを著しく阻害しました。学校は、子どもたちが安心して学び、成長できる安全な場所であるべきです。しかし、学校が機能不全に陥ることで、子どもたちは学ぶ喜びを失い、学習への意欲を削がれたかもしれません。

これは、単なる思想教育の問題にとどまらず、子どもの発達保障という教育の根本的な役割を放棄したに等しい行為です。特定の思想に偏った教育を受けた子どもたちは、異なる意見や価値観を持つ人々を理解しにくくなったり、社会の複雑性を認識できなくなったりする危険性をはらんでいます。
これにより、社会に出てから、多様な情報の中から真実を見抜き、自らの頭で判断する能力が十分に育まれない可能性も指摘できます。
思想の自由とは、多様な選択肢の中から自ら判断する力を育むことであり、一方的な思想の押し付けではありません。
3. 教員の専門職としての倫理の欠如
教員は、その専門職として、児童生徒の最善の利益を追求し、彼らの成長発達を第一に考える倫理的責任を負っています。しかし、日教組の活動は、この倫理に反し、児童生徒を自らの政治的・思想的活動の道具として利用したと見なすことができます。
特に、子どもたちが無邪気に取り組む活動の背後に、大人の政治的意図があったとすれば、これは教員としての信頼を大きく損なう行為です。また、学校が崩壊していたという事態は、教員が教育者としての責任を十分に果たしていなかった可能性を示唆します。

教員は、子どもたちの可能性を最大限に引き出すために、常に中立的かつ客観的な立場を保ち、特定の主義主張を押し付けるべきではありません。
教員は、子どもたちの「考える力」を育むことに徹するべきであり、自身の思想を植え付けることは控えるべきです。
4. 保護者や国民の信頼の喪失
日教組の偏った教育活動、そして学校の機能不全は、多くの保護者や国民からの批判と不信を招きました。学校は、保護者や地域社会と連携し、子どもたちの健やかな成長を支える場であるべきです。
しかし、特定の思想を押し付けるような教育や、授業が成り立たない環境は、保護者が子どもに望む教育と乖離し、結果として学校教育全体に対する信頼を揺るがしました。これにより、教育現場と保護者、さらには社会全体との間の溝が深まる結果となりました。
公教育に対する信頼が損なわれることは、ひいては社会全体の教育水準の低下にも繋がりかねません。

結び
筆者が小学6年生の時に体験された日教組の具体的活動、そして学校の崩壊という状況は、単なる過去の出来事として片付けられるものではありません。それは、教育の政治的中立性、児童の健全な思想形成、学習機会の保障、そして教員の専門職としての倫理という、教育の根幹に関わる重要な問題を提起しています。
日教組は、過去の歴史を踏まえ、平和と民主主義を追求する教育の重要性を主張してきましたが、その活動が特定の思想に偏り、子どもたちに一方的な価値観を押し付ける形で行われたのであれば、その責任は重いと言わざるを得ません。

教育は、未来を担う子どもたちが、多様な価値観を理解し、自ら考え、判断し、行動できる自立した人間として成長するための土台を築く場です。そのためには、教師は常に中立的な立場で、子どもたちに幅広い知識と視点を提供し、探求心を刺激するような教育を行う責任があります。
筆者の体験は、私たちに、教育が常にその本来の目的から逸脱せず、未来の社会を豊かにする人材を育成することに注力すべきであるという、重要な教訓を与えています。