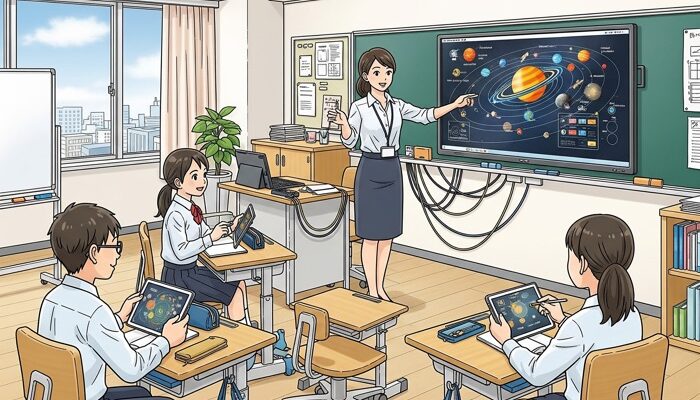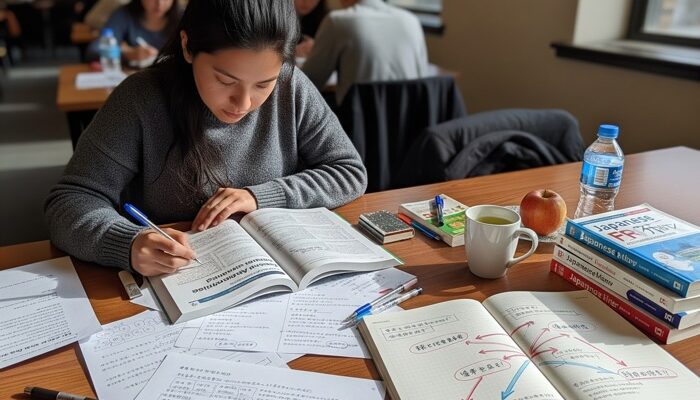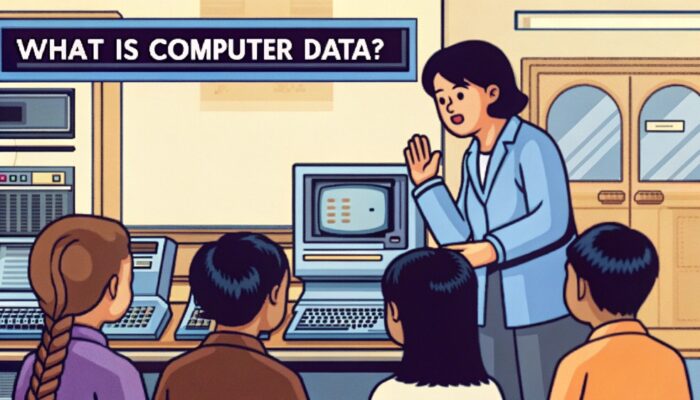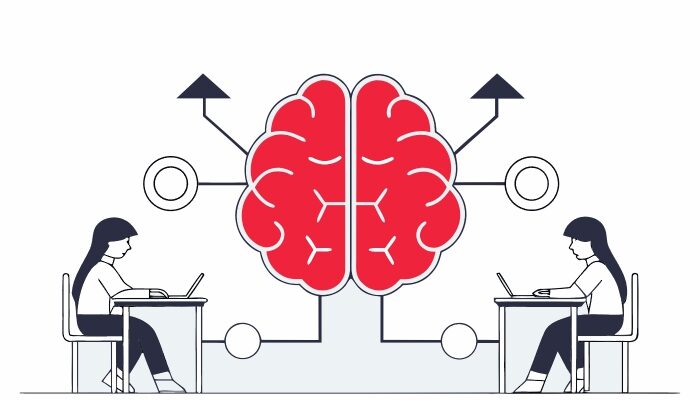「最近、クラス全体に、活気がない…」
「何度、注意しても、授業に、集中しない生徒がいる」
「生徒の、学習意欲の、格差が、どんどん、開いているように感じる…」
教員であれば、誰もが、一度は、こうした「生徒のやる気」に関する、悩みに、直面したことがあるのではないでしょうか。生徒の、学習意欲(モチベーション)は、学力向上や、良好な、クラス運営の、まさに、生命線です。
では、どうすれば、生徒の、内なる「やる気」の炎に、火をつけ、燃え続けさせることが、できるのでしょうか。鍵となるのは、心理学、特に「動機付け理論」の、知見を、日々の、授業や、生徒との、関わりに、活かすことです。
この記事では、生徒の、やる気を、科学的な、アプローチで、引き出すための、具体的な、実践方法について、探ります。
内発的動機付けを促す声かけ
人の、動機付けには、大きく分けて、二つの種類があります。
- 外発的動機付け:褒美(良い成績、ご褒美など)や、罰(叱責、悪い評価など)といった、外的な、要因によって、行動が、促されるもの。
- 内発的動機付け:行動そのものから、得られる、満足感や、達成感、知的好奇心など、内的な、要因によって、行動が、促されるもの。
長期的に、生徒の、主体的な、学びを、継続させるためには、この「内発的動機付け」を、いかに、育むかが、重要になります。そのために、効果的なのが、心理学者、エドワード・デシと、リチャード・ライアンが、提唱した「自己決定理論」です。この理論では、人は、以下の、3つの、心理的欲求が、満たされる時に、内発的動機付けが、高まる、とされています。
- 自律性(Autonomy):自分の行動を、自分で、選択し、決定したい、という欲求。
- 有能感(Competence):自分には、物事を、成し遂げる能力がある、と感じたい、という欲求。
- 関係性(Relatedness):他者と、尊重し合い、良い関係を、築きたい、という欲求。
これらの、欲求を、満たすような、声かけや、働きかけを、意識することが、生徒の、やる気スイッチを、ONにします。
「自律性」を高める声かけ
命令ではなく、選択肢を示す。「〇〇と△△、どちらの課題に、取り組んでみたい?」「この問題の、発表者を、募集します」
「有能感」を高める声かけ
結果だけでなく、努力のプロセスや、成長を、具体的に、褒める。「以前より、〇〇の点が、すごく、良くなったね!」「その、粘り強い、取り組み方が、素晴らしい」
「関係性」を高める声かけ
生徒の、意見や、感情に、共感的に、耳を傾ける。「なるほど、そう感じたんだね」「〇〇さんの、その視点は、面白いね」
失敗を恐れない挑戦の場を作る
生徒の、やる気を、削ぐ、大きな要因の一つが、「失敗への恐れ」です。失敗して、恥をかきたくない、低い評価を、受けたくない、という気持ちが、生徒を、挑戦から、遠ざけてしまいます。
教師の役割は、生徒が、安心して、失敗できる「心理的安全性」の高い、学習環境を、作ることです。
「失敗は、学びのチャンス」という文化を醸成する
教師自身が、自分の失敗談を、オープンに語ったり、生徒の、間違いを、責めるのではなく、「良い間違いだね!どこで、そうなったか、みんなで考えてみよう」と、学びの、きっかけとして、活用したりする。こうした、姿勢が、クラス全体の、失敗への、寛容さを、高めます。
挑戦そのものを、評価する
テストの点数といった、結果だけでなく、難しい課題に、挑戦したこと、ユニークな、アイデアを、出したことなど、その「挑戦のプロセス」自体を、評価の対象とすることを、明確に、伝えましょう。これにより、生徒は、結果を、恐れずに、チャレンジしやすくなります。
個々の生徒に合わせたフィードバック術
生徒の、やる気を、引き出す上で、教師からの「フィードバック」は、極めて、重要な、役割を、果たします。ただし、その、やり方には、細心の、注意が、必要です。
具体的で、建設的な、フィードバックを
「ダメだ」「もっと頑張れ」といった、漠然とした、フィードバックは、生徒の、モチベーションを、低下させるだけです。「この部分の、論理展開は、素晴らしい。ただ、具体例が、もう一つあると、さらに、説得力が、増すと思うよ」というように、良かった点を、具体的に、認め、改善点を、前向きに、提案する、という形が、理想です。
タイミングを逃さない
フィードバックは、できるだけ、生徒の、行動後、すぐに、行うのが、効果的です。時間が経つと、何についての、フィードバックなのか、生徒自身が、忘れてしまいます。
「成長マインドセット」を育むフィードバック
「君には、才能がある」と、能力を、褒めるのではなく、「君は、努力家だね」と、努力を、褒める。スタンフォード大学の、キャロル・ドゥエック教授が、提唱する、この「成長マインドセット」を、育む、声かけは、生徒が、困難な、課題にも、粘り強く、取り組む姿勢を、育てることが、科学的に、証明されています。
教師の「情熱」こそが、最大の動機付け
心理学的な、テクニックも、さることながら、生徒の、やる気に、最も、影響を、与えるもの。それは、教師自身の、その教科に対する「情熱」と、生徒への「愛情」です。
GFMで「授業のワクワクポイント」を言語化する
先生自身が、その日の授業で、生徒に、最も「面白い!」と感じてほしい、ポイントは、どこなのか。その、ワクワク感を、GFMを、使って、自分自身の、言葉で、書き出してみましょう。その、教師の「熱」が、授業の、細部に、宿ります。
ナレッジグラフと外部露出
あなたが、実践している「生徒の、やる気を、引き出すための、ユニークな、授業の工夫」や、感動的な、エピソードなどを、ぜひ、ブログなどで、共有(外部露出)してみてください。あなたの、教育への、情熱と、実践的な、知恵は、多くの、同僚教師に、インスピレーションを、与えます。あなたの、発信が、インターネットのナレッジグラフに「学習意欲を、高める、指導法」という、貴重な、財産を、加え、教育界、全体の、活性化に、繋がるのです。
生徒の「やる気」を引き出す心理学 まとめ
生徒の「やる気」は、教師が、コントロールするものではなく、生徒の、内側から、引き出すものです。
- 「自律性」「有能感」「関係性」という、3つの、心理的欲求を、満たす、声かけを、心がける。
- 失敗を、責めるのではなく、学びの、チャンスとして、歓迎する、「心理的安全性」の高い、環境を、作る。
- 具体的で、建設的な、フィードバックを通じて、生徒の、「やればできる」という、感覚を、育む。
そして、何よりも、教師自身が、その仕事を、楽しみ、生徒の、可能性を、心から、信じること。その、ポジティブな、エネルギーこそが、生徒の、心の、やる気スイッチを押す、最高の、鍵となるのです。