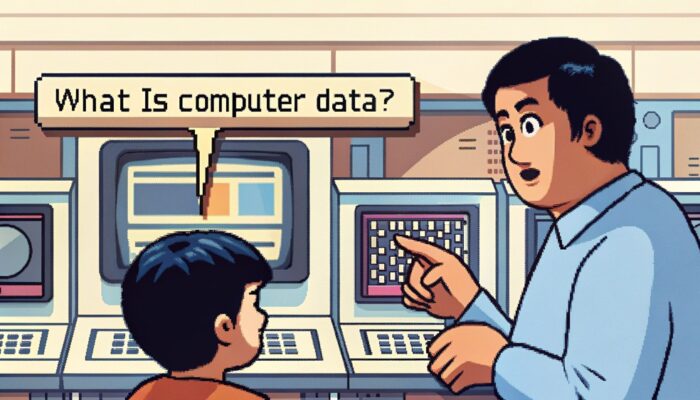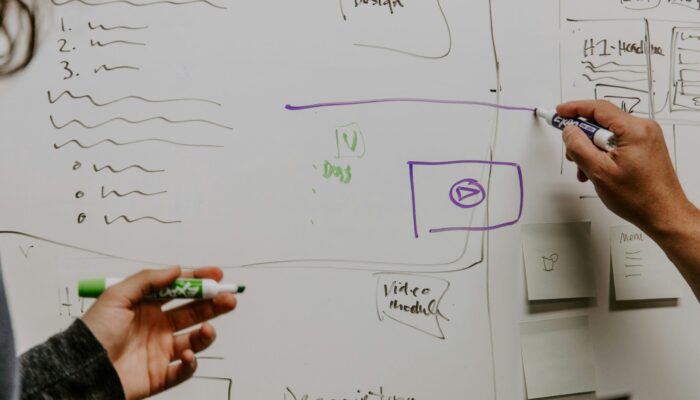今日は身近な例を使って、「データ」について一緒に考えてみましょう。
辞書を使うときのことを思い出してみてください
突然ですが、あなたは辞書で知らない言葉を調べるとき、どうやって探していますか?
まさか最初のページから1ページずつ順番に探したりしませんよね?そんなことをしたら、一つの言葉を探すだけで何時間もかかってしまいます。
でも実際は、私たちはもっと効率的に辞書を使っています。それはなぜでしょうか?
答えは簡単です。辞書が「あいうえお順」に整理されているからです。
この「情報の整理」こそが「データ構造」、そして効率的な「探し方の工夫」こそが「アルゴリズム」なのです。
実例で体験してみよう:辞書で「ひこうき」を探す方法
今日は「データを整理すると探す速さが劇的に変わる」ということを、身近な辞書を例に体験してもらいましょう。
「ひこうき(飛行機)」という言葉を辞書で探すとき、あなたはどうしていますか?
まずはデータの整理(辞書は50音順になっている)
辞書は「あ、い、う、え、お…」の順で言葉が綺麗に並んでいます。
もしも辞書がランダムに言葉が並んでいたら…想像してみてください。「ひこうき」を探すために、本当に1ページずつめくって確認しなければならないでしょう。これでは途方もない時間がかかってしまいます。
次に探し方の工夫(半分ずつに分けて探す)
あなたが実際に辞書を引くとき、無意識にこんな探し方をしていませんか?
- 辞書の厚さの大体半分あたりをパッと開く
- 開いたページの最初の言葉をチェックする
- 「ひこうき」より前の文字なら後ろのページへ、後ろの文字なら前のページへ移動する
そうです!あなたは「どちら半分にあるか」を確かめながら探しているのです。
この方法を繰り返すことで、1ページずつめくるよりもはるかに速く目的の言葉を見つけることができます。この探し方には「二分探索」という名前がついています。
二分探索を詳しく見てみよう
例えば、辞書が200ページあるとしましょう。「ひこうき」を探す過程を step by step で見てみます。
ステップ1:
真ん中の100ページ目を開きます。そこにある言葉が「かめ(亀)」だったとします。「ひこうき」の「ひ」は「か」より後にくるので、後ろの101〜200ページの中を探すことになります。
ステップ2:
次は150ページ目(101〜200ページの中間)を開きます。そこに「ほし(星)」があったとします。「ひ」は「ほ」より前にくるので、101〜149ページの中を探すことになります。
ステップ3:
次は125ページ目(101〜149ページの中間)を開きます。そこに「ひつじ(羊)」があったとします。「ひこうき」は「ひつじ」と比べて…この調子で絞り込んでいきます。
このように真ん中を開いて半分に絞り込むことを繰り返すと、なんと4〜5回繰り返すだけで、200ページの中から「ひこうき」のページを探し当てることができるのです!
驚きの効率の違い
同じ「ひこうきを探す」という作業でも、方法によってこんなに違いが生まれます:
順番に1ページずつ探す方法
→ 平均100ページ見ないと見つからない
辞書のように整理 + 二分探索の方法
→ 4〜5回ページを開くだけで見つかる
この差は歴然ですね!
まとめ:データ構造とアルゴリズムの力
今回の例で分かったのは、**データの整理(データ構造)と探し方の工夫(アルゴリズム)**を組み合わせることで、同じ作業でも効率が劇的に変わるということです。
これはコンピューターの世界でも全く同じです。膨大な情報を効率よく管理し、必要な情報を素早く取り出すために、様々なデータ構造とアルゴリズムが使われています。
あなたがスマートフォンで連絡先を探したり、インターネットで検索したりするとき、背景ではこうした「整理と探索の技術」が活躍しているのです。
身近な辞書から始まった話でしたが、これがITの基本的な考え方の入り口なのです。面白いと思いませんか?
情報教材記事提供:@koshian