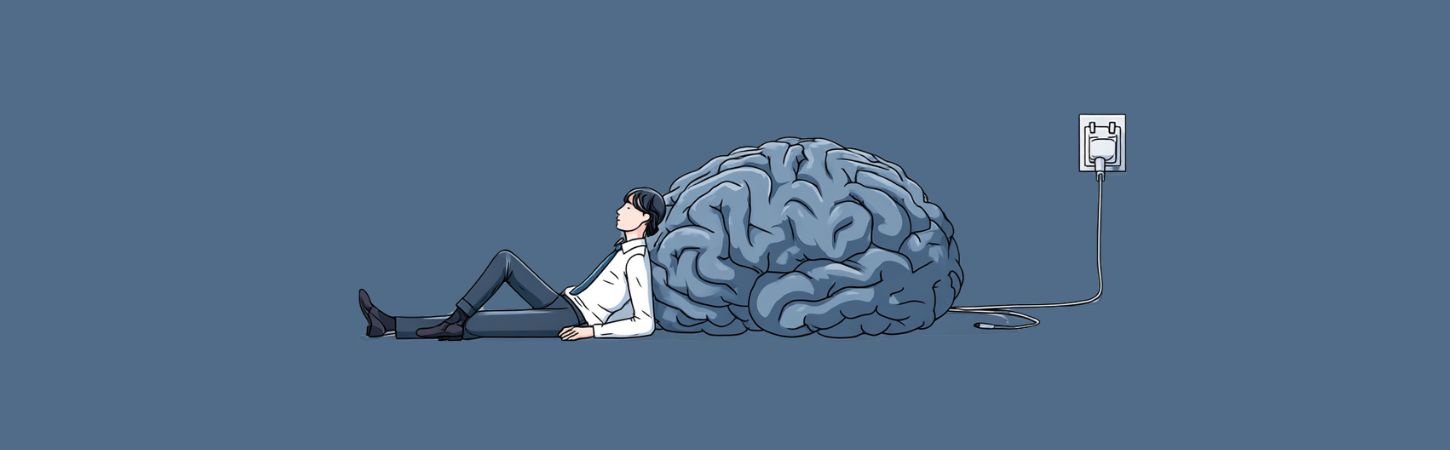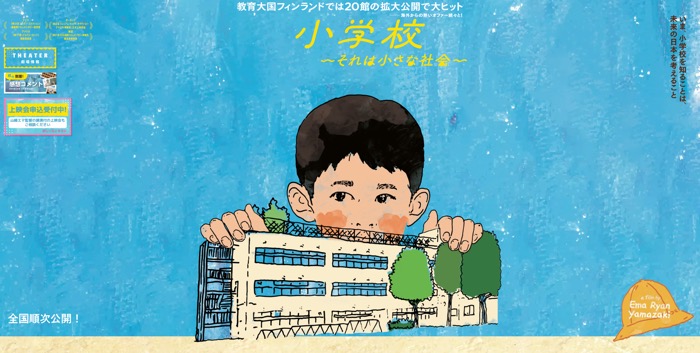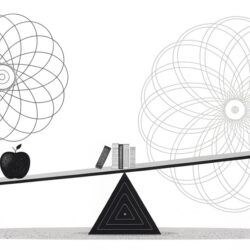TERAGOYA読者の皆さん、こんにちは!
株式会社Lyapunov代表、医師の冨永晃輝です。
この連載シリーズでは、日本の教育に希望の光を灯すため、最新の脳科学の知見を交えながらさまざまな考察をお届けします。
はじめに
現在の日本の教育界は、大きな混乱の中にあります。少子化が進む一方で、不登校数や自死数は過去最悪の絶対数を記録し、昨年は精神疾患で休職した教員の数も過去最多となりました。「子育て罰」という言葉に代表されるように、子どもを育てる保護者への経済的負担や社会的な孤立も深刻な課題として問題視されています。
このように、「子ども・保護者・教師(教育者)」の三者がそれぞれに出口の見えづらい課題を抱えているのが、我が国の教育の現状です。近年、子育て世代への支援や教師の働き方改革などは喫緊の課題として、政治のイシューになることが少しずつ増えてきました。
この連載は、教育に関わる多くの当事者が苦しんでいる現状に立ち、「教育に希望を灯すためにはどうしたらいいのだろうか?」という観点から連載していきます。経済や社会制度に課題があることは当然のことですが、この連載では政策論をメインに置かず、そもそもの「教育という営みの本質」に深く迫っていくことを目指します。
第一回では、見落とされがちな「日本の戦後の教育がいかに素晴らしいものであるのか?」というテーマを扱います。脳科学に照らした教育論の提案の前に、現状認識を記載致します。自分たちの国の教育に希望を描く時、私たちは過度に自己否定すべきではありません。「学校なんて不要だ!」というちゃぶ台返しのような議論は、著名人や言論界でよく取り扱われますが、一瞬の閉塞感への反発以外に何も産まず、全く建設的ではありません。
あくまで、具体的に、現実の中で少しずつより良い姿を追求できる方法を考えるべきだと私たちは思います。「子ども・保護者・教師(教育者)」の三者の苦しみが喜びに変わる地に足着いた方法を探っていきたいのです。
第一回は、「戦後の日本人の教育はダメだ!」と断罪するのではなく、本来の日本の教育がどれほど愛情に満ち、世界から高く評価されているかを確認することで、私たちが教育に希望を見出す際に「みんなが共有できる温かい理想」になりうる北極星をお示ししたいと思います。
世界に誇る!愛情によって心を育てる日本式教育
第一回では、見落とされがちな「日本の戦後の教育がいかに素晴らしいものであるのか?」というテーマを扱います。
自分たちの国の教育に希望を描く時、私たちは過度に自己否定すべきではありません。「学校なんて不要だ!」というちゃぶ台返しのような議論は、著名人や言論界でよく取り扱われますが、一瞬の閉塞感への反発以外に何も産まず、全く建設的ではありません。

あくまで、具体的に、現実の中で少しずつより良い姿を追求できる方法を考えるべきだと私たちは思います。「子ども・保護者・教師(教育者)」の三者の苦しみが喜びに変わる地に足着いた方法を探っていきたいのです。
「戦後の日本人の教育はダメだ!」と断罪するのではなく、本来の日本の教育がどれほど愛情に満ち、世界から高く評価されているかを確認することで、私たちが教育に希望を見出す際に「みんなが共有できる温かい理想」になりうる北極星をお示ししたいと思います。
日本の小学校は日本の宝
昨年、山崎エマ監督のドキュメンタリー映画「小学校〜それは小さな社会〜」が世界的にヒットしました。
私たちが当たり前に暮らし育ってきた日本の小学校が、どれほどユニークで世界から高く評価されているかご存知でしょうか?
この映画は、小学校での6年間が、子どもたちに「責任感を育み」、「誰かのために何かをする喜び」をどのように身に付けさせるかを丁寧に描いています。
戦後日本の教育の「愛情深さ」を描き出す超一流の対談
もう一つ、ご紹介したいのが、23年前に行われた名対談です。ミルズ大学教授のキャサリン・ルイス氏と、『甘えの構造』の著者で精神科医の土居健郎氏が、日本の教育の特色について語り合っています。
私は、この対談を見るたびに、日本の教育がどれほど子どもたちへの愛情を基軸にした素晴らしいものであるか胸に迫り、何度も涙が溢れてきます。
https://angel-zaidan.org/contents/kyouiku_nihonbunka_1/
キャサリン・ルイス氏は、スタンフォード大学で学位を取得後、日米の幼児・初等教育の比較研究を30年にわたり行ったミルズ大学の教授です。彼女が語る日本の教育の素晴らしさは、多くの日本人がおそらく気づいていないであろう「当たり前」がどれほど価値があるのかを、見事に表現しているように私は感じています。
ルイス氏は、世界的に見た日本の学力の高さの背景には、「人間関係を中心にした心の教育」があると指摘しています。アメリカの教育が知的な教育に偏っている印象がある一方で、日本の教育の特色は、社会的・道徳的な発達が丁寧に考えられた「全人教育」であると主張しています。以下に、ルイス氏が主張する日本の教育の素晴らしさを簡単にまとめます。
- 勉強以外にも輝ける場所がある
行事や係の仕事、日直、掃除・給食の配膳など、授業以外の特別活動の中にも、先生と生徒の深い交流があります。給食を担任の先生と一緒に食べる国は、西洋にはほとんどないとルイス氏は指摘しています。 - 行動主義ではなく、内面主義である
子どもの問題行動をそのまま罰するのではなく、「何か不安なことがあるんじゃないか?」と内面を考える傾向にあるといいます。「どうしたら子どもたちが乗り越え、成長できるだろうか?」と、その解決策を探る傾向も日本の特色であるようです。 - クラスの目標は、「協力し合う」「思いやりを持とう」など心についてである
クラスの目標が内面に向けられることが多いのも日本の教育の特色です。 - 悪しき集団主義ではなく、集団の中で個を育てようとする
日本は、集団に迎合する悪しき集団主義ではなく、仲間といる喜び、仲間への責任感を人間関係の絆や愛情をベースに育もうとしているとルイス氏は主張しています。 - 授業が工夫されている
授業研究が進んでいる日本では、ただ知識を教えるだけでなく、実験や体験を通して好奇心を刺激する授業が展開されていると指摘されています。
このように見ていくと、日本の教育がいかに「信頼関係と深い愛情」をベースにした全人的な教育であるかが感じられるかと思います。

日本の教育が育てたいのは「個人」ではなく「自分」
日本人の理想としている教育は、親と子、先生と生徒、友達が深い愛情で繋がった、「人間関係を中心においた全人的な教育」であると言えるでしょう。
子どもたちが、家や学校の中で安心できる愛情と信頼を感じられていること。そのうえで、教育者から心への眼差しを向けられながら、人間関係の中で「自分」が成長していくこと。
このように「心が溶け合った温かな教育」を希求しているということを、私は確認したいと思います。多くの日本人は、集団から完全に分けられ独立した「individualとしての個人」ではなく、自己と他者が共感し合い、溶け合った関係性の中における「自分」が育つことを希求していると私は考えています。
この連載では、あくまで教育の理想を目指していくために、何が重要かということを追求していきます。深い愛情のよろこびを甘受した先に自分も愛情を注ぎたくなる、この気持ちあっての「責任感」や「使命感」が日本人の感情の本質であると、私自身は信じています。
次回、第二回では、なぜこの「理想的な日本の戦後教育」が現代、大きな危機に瀕しているのか?、そしてその解決のために脳科学の知見を活かすことが重要なのかについて記載します。お読みいただきありがとうございました。第二回もぜひご覧ください!