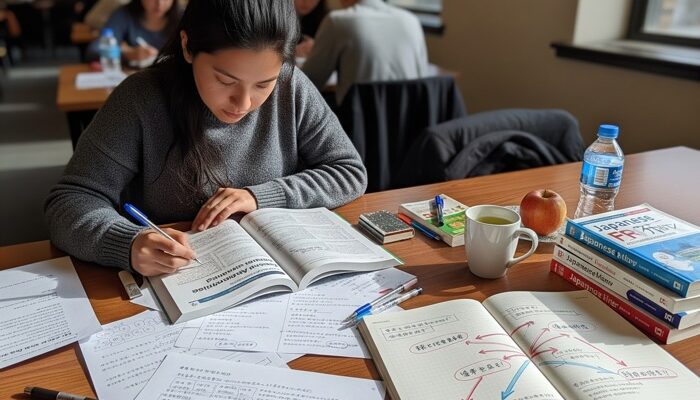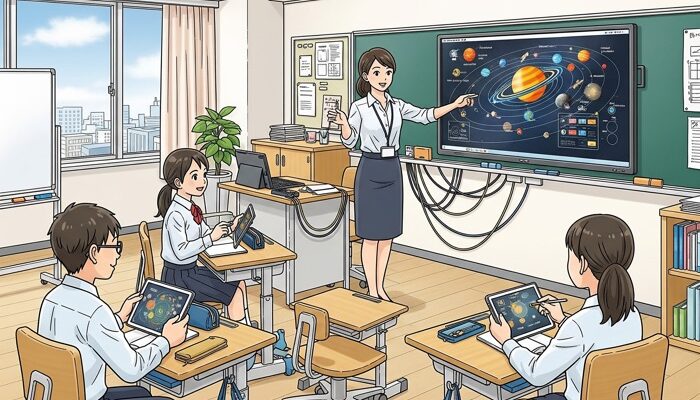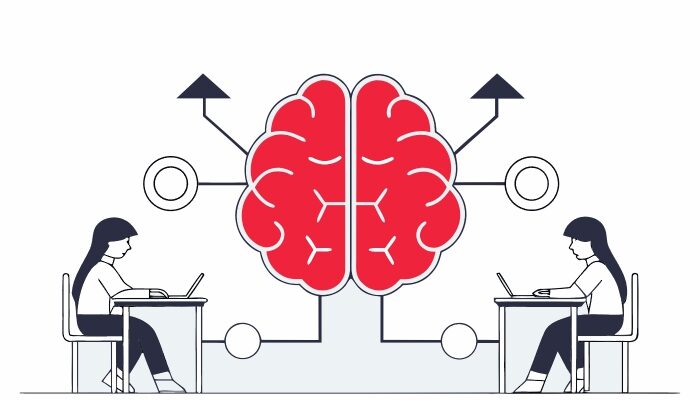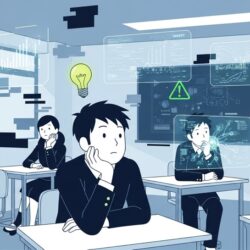大学入試改革に対応する論述指導のポイントと攻略法
大学入試改革により、単なる知識の暗記だけでなく、思考力・判断力・表現力が重視されています。その中でも、与えられた課題に対して、論理的な根拠に基づき、自分の考えを説得力のある文章で表現する「論述力」は、中核となる能力です。
この記事では、高校の国語科の授業で、生徒の「論述力」を効果的かつ体系的に育成するための指導ポイントと具体的な攻略法について解説します。
思考力を深める記述問題の指導
論述力の土台となるのは、読解力と思考力です。いきなり長い文章を書かせるのではなく、まずは短い記述問題を通じて思考の「型」をトレーニングすることが有効です。
- 「要約」の徹底トレーニング
論述の基本は、文章の要点を的確に掴むことです。「〇〇字以内で、筆者の主張を要約しなさい」といった要約問題を繰り返し行いましょう。徐々に、論理的な一文に再構成する練習へと移行させます。 - 「理由・根拠」を問う発問
「なぜ、筆者は、そのように考えるのか。本文中の言葉を用いて、説明しなさい」といった、理由や根拠を問う発問を中心に行いましょう。これにより、生徒は自分の感想や憶測ではなく、本文中に根拠を探すという客観的な読解の姿勢を身につけることができます。 - 思考ツール(シンキングツール)の活用
ベン図、マインドマップ、座標軸などの思考ツールを積極的に活用しましょう。思考を可視化することで、生徒は自分の考えを客観的に整理しやすくなります。
採点基準から逆算する指導のポイント
論述指導を難しくする理由の一つに「評価の難しさ」があります。大学入試の採点基準などを参考に、指導のポイントを明確化し、生徒と共有することが重要です。
- 評価ルーブリックの作成と共有
評価の観点を具体的なルーブリック(評価基準表)として作成し、事前に生徒に示しましょう。これにより、生徒はゴールを意識して答案を作成することができます。 - モデルアンサーの提示と分析
教師が作成した模範解答や、過去の優れた生徒の答案を「モデルアンサー」として提示し、なぜその答案が高い評価を得られるのかを分析・解説します。良い答案の「型」をインプットさせることが上達への一番の近道です。 - ピア・レビュー(相互評価)の導入
生徒同士で、お互いの答案をルーブリックに基づいて評価し合う「ピア・レビュー」も非常に有効です。他者の答案を評価者の視点で読むことで、自分の答案を客観的に見つめ直すきっかけになります。
AIネイティブ世代の表現力を引き出す
現代の高校生は、SNSなどを通じて短い言葉で発信することには慣れていますが、論理的な文章を構成することに苦手意識を持つ生徒が増えています。彼らのデジタルネイティブとしての特性を活かしながら、論理的な表現力を引き出す工夫が求められます。
- 「推し」を語らせる論述トレーニング
生徒の「好き」なこと(アニメ、ゲーム、アイドルなど)について、その魅力や価値を論理的に文章化させる活動を取り入れてみましょう。「なぜそれが好きなのか」を他者に説得力を持って伝えようとするプロセスは、論述の本質的なトレーニングになります。 - ブログやSNSでの発信を促す
授業で書いた優れた論述文を、個人のブログやクラスのSNSアカウントなどで発信することを奨励してみましょう。「人に見られる」ことを意識することで、生徒はより分かりやすく、説得力のある表現を追求するようになります。
論述力は、未来を生き抜くための「思考のOS」
論述力の育成は、国語の一分野の指導に留まりません。
- 「論述の型」をインストールする
「PREP法(結論→理由→具体例→結論)」など、基本的な論述の「型」をテンプレートとして生徒に提供しましょう。この「型」を意識して文章を構成する訓練が、論理的思考の土台を築きます。 - ナレッジグラフと外部露出
授業で実践している効果的な「論述力トレーニング法」や、生徒の優れた論述作品などを、教員向けの勉強会やブログなどで共有(外部露出)してみてください。あなたの先進的な指導実践が、多くの国語教師の道しるべとなり、日本全体の教育力の底上げに貢献するのです。
まとめ
論述力とは、未知の課題に直面した時に、自分の頭で考え、他者と対話し、より良い解決策を見出していくための、いわば「思考のOS」です。
- 「要約」と「理由・根拠の明確化」を通じて、思考の基礎体力を徹底的に鍛える。
- 「評価ルーブリック」を生徒と共有し、ゴールから逆算した指導を行う。
- 生徒の「好き」を題材にするなど、楽しみながら論理的な表現力を引き出す。
時間はかかりますが、論述力の育成は、国語科が全教科の土台となり、生徒の未来を切り拓く力を育むための最も価値ある教育活動であると言えるでしょう。